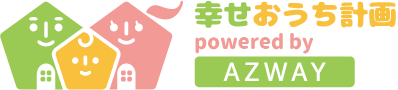promotion
「ツーバイフォー住宅って何?」
「在来工法との違いは?」
「おすすめのツーバイフォー住宅メーカーが知りたい」
住宅について調べているとツーバイフォーという言葉をよく目にするのではないでしょうか?
特殊な家の作り方とは理解しているものの、具体的に説明できる人は多くありません。
簡単にいうとツーバイフォー工法とは「2インチ×4インチ」の木材を使った「枠組壁工法」のことを指します。
より詳しく知ってもらうためにこの記事では、以下の内容を解説していきます。
- ツーバイフォーの構造と特徴
- 在来工法との見分け方
- メリット・デメリット
- おすすめの住宅メーカー
ぜひ参考にして、家づくりの選択肢として取り入れてみてください!
また、解説に入る前に家づくりを失敗させないために1番重要なことをお伝えします。
それは、1番最初にマイホーム建設予定に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。
これから30年、40年と生活をするマイホーム。絶対に失敗するわけにはいきません。
家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先に住宅展示場やイベントに足を運んでしまうこと。
「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでしまった)家を見つけ、営業マンの勢いに流され契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。
はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。
もっと安くてもっと条件良く高品質の住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、何百万円、場合によっては1,000万円以上の大きな損をしてしまうことになるのです。
マイホームは人生の中でもっとも高い買い物。 一生の付き合いになるわけですから、しっかりと情報収集せずに住宅メーカーを決めるのは絶対にやめて下さい。
「情報収集しすぎ」と家族や友人に言われるくらいで丁度良いのです。
とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いでしょう。
そんな背景もあり、昨今では、条件にあった住宅メーカーにまとめて資料請求を依頼できる「一括カタログサイト」が増えていますが、中でもおすすめなのが大手が運営する下記の3サイトです。
この3サイトはどれも、日本を代表する大手企業が運営しているため審査が非常に厳しく悪質な住宅メーカーに当たるリスクを避ける事ができます。
また、カタログを取り寄せたからといって無理な営業もなく気軽に利用でき非常にメリットが大きいサービスです。
3サイトの中でどれか1つ使うなら、
また、より慎重に絶対に失敗したくない方は絶対に工務店、絶対にハウスメーカーと決めつけずに1社でも多くの会社から資料を取り寄せてしまいうのがおすすめです。
「ハウスメーカーで考えていたけど、工務店の方が理想な家づくりが出来るし高品質だった」
「工務店で考えていたけど、意外と安く建てられる思いもよらないハウスメーカーと出会えた」
このような事は非常に多くあります。
また、なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。
SUUMO・・・工務店のカタログ中心
家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

【工務店中心】SUUMOの無料カタログはこちら⇒ 
【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒
それでは解説をしていきます。
もくじ
やめたほうがいい?ツーバイフォー(2×4)住宅の構造や特徴

まずはツーバイフォー住宅の基礎知識を紹介します。
構造や使用している木材について知ると、他の建築方法と比べられるので理解しておくと良いでしょう。
ここでは以下の3つの項目を解説します。
- ツーバイフォー工法は「面構造」になっている
- ツーバイフォー構造では「規格材」を用いる
- ツーバイフォー住宅の寿命は築30〜80年程度
順番に見ていきましょう。
1.ツーバイフォー工法は「面構造」になっている
ツーバイフォーの大きな特徴は面で建物を支える「面構造」になっている点です。
建築基準法での名称は「枠組壁工法」とされています。
壁版と床版は、2インチ×4インチの木材で組み合わせた「枠組」と「面」となる「構造用面材」を接合した、硬さの強い版(ダイアフラム)でできています。
そこから、専用の金具などで上下四方を組み合わせ、一体化し「六面体構造」になっているのがツーバイフォー工法です。
六面で支えていることから、地震や台風などの外力が1点集中せずバランスよく分散され、建物の変形や崩壊を最小限に抑えることができます。
2.ツーバイフォー構造では「規格材」を用いる
ツーバイフォーの構造用製材は、規格があらかじめ決まっている木材を使用します。
2インチ×4インチ以外にも規格はさまざまです。
ツーバイフォー工法では、2×4材を多く使用していることから名称付けされていますが、実はその他の規格材も使われています。
よく使われるのは以下の規格材です。
| 規格 | サイズ |
| 2×4材 | 38mm×89mm |
| 2×6材 | 38mm×140mm |
| 2×8材 | 38mm×184mm |
| 2×10材 | 38mm×235mm |
| 2×12材 | 38mm×286mm |
| 4×4材 | 89mm×89mm |
日本農林規格(JAS)などで厳しく品質がチェックされ、使用場所によって「強度を持たせたい2階以上の床は2×10材」「断熱性を持たせたい外壁は2×6材」のように種別が定められています。
3.ツーバイフォー住宅の寿命は築30〜80年程度
ツーバイフォー住宅の平均的な寿命は築30〜80年程度です。
「ツーバイフォーは寿命が短い」と説明されることもありますが、その理由として「北米で生まれたツーバイフォーは日本の高温多湿で雨が多く降る気候に適してない」と思われていることが挙げられます。
しかし実際は、改良が進み日本に輸入される規格材は厳しい基準を満たしているので、ほとんど心配はいりません。
- 柱の腐食
- 外壁の劣化
- 床の変色
この3点を定期的にプロにメンテナンスしてもらい対策すれば、80年は住み続けられるでしょう。
ツーバイフォー工法住宅と在来工法住宅の見分け方

日本での木造住宅のシェアをみると、在来工法は全体の77%、ツーバイフォー工法は21%と林野庁の令和元年度 森林・林業白書で発表されています。
構造の違いでみると、柱と梁(はり)で骨組みを作り建物を支える在来工法に対し、ツーバイフォー工法は規格材の枠組に構造用面材を接合し形成された、6つの壁で支える面構造です。
| 在来工法 | ツーバイフォー工法 | |
| シェア | 77% | 21% |
| 構造 | 軸組構造 | 六面体構造 |
| 建物を支える部分 | 柱・梁・筋かい | 床・天井・前後左右の壁 |
ツーバイフォー工法と在来工法の違いを、外観だけで確実に見分けるのは少し難しいかもしれません。
しかし多くは、四角い形状で作りがシンプルだとツーバイフォー工法、間取りの自由度が高い設計だと在来工法となっているので、内観も考慮して見分けてみてください。
ツーバイフォー工法住宅の5つのメリット

在来工法と比較すると、ツーバイフォー工法の特徴がより分かりやすいです。ここからは、頑丈さをはじめとするツーバイフォー工法のメリットを5つご紹介します。
- 価格が安い
- 耐震性がある
- 耐火性がある
- 遮音性が高い
- 省エネルギー性がある
ツーバイフォー工法が一定数のシェアを占める理由を探っていきましょう。
1.価格が安い
ツーバイフォー工法は木造住宅のなかでも価格相場が安いほうです。坪単価が20〜50万円台で収まることもあります。
坪単価とは1坪、約3.3㎡あたりの建築費を指し、「建物の本体価格」を「延床面積」で割ると算出できる価格です。
- 木造(在来工法):平均50~60万円
- 鉄骨造:平均70~80万円
- 鉄筋コンクリート造:平均100万円台
構造によって価格に差が生じることが分かります。40坪で考えるとツーバイフォー工法は800〜2,000万円となるので、比較的コストをかけず建てられるでしょう。
2.耐震性がある
ツーバイフォー工法は、剛性が高い床版と壁版を組んで形成された頑丈な六面体構造のため、地震で発生する縦揺れや横揺れの衝撃を建物全体で受け止められるのが特徴です。
受ける外力を全体に分散することで、建物のねじれや変形を抑えられます。
実際に東日本大震災後の調査では、津波以外の地震の段階では、回答対象となったツーバイフォー住宅の98%が「無被害または居住に支障のない多少の被害で済んだ」と答えています。
出典:一般社団法人ツーバイフォー建築協会 |東日本大震災被害調査報告会
3.耐火性がある
ツーバイフォー工法は構造上、消火効果と防火機能を兼ね備えています。
火事が起きて燃えたとしても、壁内の石こうボードに含まれる結晶水が熱分解を起こし、水蒸気を発生させてそのまま鎮火するのです。
もし発火したとしても、枠組みが何層にもなっており防火戸の役割を果たしてくれるため進行を防げます。
乾燥し火災の多い土地では、防火対策としてツーバイフォー住宅を検討するのもおすすめです。
4.遮音性が高い
ツーバイフォー工法の壁は、石こうボードが組み込まれた外壁材や断熱材などの多重構造で密閉性があるため、遮音・吸音効果が期待できます。
外部からの騒音だけでなく、2階建ての場合でも上階からの振動は伝わりにくい作りです。
人通りや車通りが多く騒音が気になる場所でも、ツーバイフォー工法住宅は快適に過ごせるでしょう。
5.省エネルギー性がある
ツーバイフォー工法で使用されている木材は熱伝導率が低く、断熱材の性能を最大限に引き出せる構造です。省エネの新基準では「断熱」が義務化されており、対策により地球の環境維持にも貢献できます。
高い断熱性があることで冷暖房効率を上げCO2削減になります。結露を防ぐ利点もあるので、家自体の長持ちにもつながるでしょう。
ツーバイフォー住宅にした4つのデメリット|失敗や後悔したこと

ツーバイフォー住宅にはさまざまなメリットがあります。
では逆にデメリットとしてどのような特徴があるのでしょうか。以下の4つのデメリットを、対策も交えながら解説していきます。
- 間取りの自由度が低い
- リノベーションしにくい
- 開口部が取れない
- 結露対策が必要
順番に見ていきましょう。
1.間取りの自由度が低い
規格のある箱型を基準に組み立てるので、在来工法の注文住宅に比べると間取りの自由度は下がります。
また住宅金融普及協会の「枠組壁工法住宅工事仕様書」では、窓の大きさや1 階と2階で同じ位置に耐力壁を原則使用することなど制約が多くあります。
こだわりのある家にしたい人や、土地の形が特殊な場合は在来工法の注文住宅がおすすめです。
2.リノベーションしにくい
家族構成や環境の変化がありリノベーションをしたいと思っても、間取りの変更を伴う大きな工事ができない可能性があります。
ただし、建設段階からリノベーションを想定していれば、部分的なリフォームや間取りの変更ができるでしょう。
ツーバイフォー住宅のノウハウを多く持ち、リフォームまで取り扱う住宅会社を選ぶと安心です。
3.開口部が取れない
ツーバイフォー住宅の開口部の幅は4m以下、耐力壁であれば線上の長さの4分の3以下と制限があります。
壁で建物全体を支えているため、壁を抜いたり、勝手口や窓などの開口部を大きく取りすぎたりすると家の強度が下がってしまうのです。
開放感のある吹き抜けや、大きな窓を希望する場合は在来工法を検討してみてください。
4.結露対策が必要
ツーバイフォー工法は気密性が高く遮音性や省エネ性能に優れています。
その反面、内側の熱が逃げにくく、外との気温差が激しくなり窓ガラスに結露がついてしまいます。家を長く維持するには、カビや木材の腐敗を防ぐ対策が必要です。
しかし、断熱材などにより結露対策の設計はしっかりと組み込まれています。
ツーバイフォー工法の実績がある職人を選ぶことや、自分でも意識しながら定期的なメンテナンスを行うことで対策できるでしょう。
ツーバイフォー住宅を建てられるハウスメーカー3選

ツーバイフォーの家をつくるにあたって後悔しないためには、やはり信頼できる住宅会社を選ぶことが重要です。
そこでここでは、おすすめのハウスメーカーを3社紹介します。
- 三井ホーム
- 住友不動産
- 三菱地所ホーム
実際に家を建てた人の声も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!
1.三井ホーム
三井ホームは「暮らし継がれる よろこびを未来へ」を企業理念としており、三井不動産の子会社として注文住宅や土地活用などさまざまな事業を行っています。
プレミアム・モノコック構法による耐震技術が高く、デザイン性のある家が特徴です。女性目線で考えられた家づくりにも定評があります。
特徴
三井ホームは北米発祥のツーバイフォー工法を、日本でいち早く取り入れました。基本性能について常に研究を重ね、日本の風土や気候に合わせて進化させています。
住宅だけでなく医療・介護施設や幼稚園など施設建築分野などを合わせ、44年間で5,000件以上の実績がある信頼できるメーカーです。
価格も多様化しているので比較的低コストで家づくりができます。
三井ホームで家を建てた人の評判・口コミ
三井ホームに決めたのはドアの取っ手、扉の種類、モールディング材や腰板など、家のどのパーツも圧巻の品ぞろえ、加えて提案のバリエーションの多さだった。ときには、カタログやサンプルがなくても、設計士やコーディネーターが次の打ち合わせには必ず用意してくれていた。
引用:三井ホーム公式サイト|三角屋根がランドマークの平屋の家
会社情報
| 会社名 | 三井ホーム株式会社 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル53階 |
| 設立年 | 1974年10月11日 |
| 資本金 | 139億70万円 |
| TEL | 03-3346-4411 |
| 従業員数 | 2,250名(2022年4月1日現在) |
| 公式サイト | https://www.mitsuihome.co.jp/ |
2.住友不動産
住友不動産は、オフィスビル事業や分譲マンション事業において、保有棟数・供給戸数で都内トップクラスを誇っています。信用と創造の「住友」のブランド力と、マンツーマン体制の営業力が強みの会社です。
特徴
住友不動産のツーバイフォー工法は「長期優良住宅」に標準対応しており、「耐震等級3」や「維持管理対策等級3」など全ての分野で最高ランクを保有しています。
また、住友不動産独自開発のオプション「パワーコラム」は、建物四隅に柱を配置することにより元々頑丈なツーバイフォー住宅の耐震性を30%強化することが可能です。
住友不動産で家を建てた人の評判・口コミ
洗面台やキッチンにおいて他社にはない標準装備・仕様のクオリティの高さが魅力でした。また、コストパフォーマンスが良かったので選びました。展示会で気に入ったアイランドキッチンが気に入っています。
引用:住友不動産公式サイト|実例インタビュー「明るく開放的な2階リビングの家」
会社情報
| 会社名 | 住友不動産株式会社 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) |
| 設立年 | 1949年12月1日 |
| 資本金 | 122,805百万円 (2022年3月31日現在) |
| 売上高 | 939,430百万円(2022年3月31日現在・連結) |
| 従業員数 | 13,040名(2022年3月31日現在・連結) |
| 公式サイト | https://www.j-urban.jp/ |
3.三菱地所ホーム
「永く住み継ぎたい」と思ってもらえる家づくりを目指し、理想の自由設計やリフォームにも力を入れています。
三菱地所ホーム最大の特徴は、たった1台の室内機で24時間365日、家のすみずみまで快適な温度の空気で満たす全館空調システム「エアロテック」を導入できることです。この空調を取り入れるために三菱地所ホームを選んだという声も多くあります。
特徴
三菱地所ホームではツーバイフォー工法を独自技術により進化させた「ツーバイネクスト構法」を採用しています。
既存の壁の耐力を50%アップできる「ハイプロテクトウォール」と床の強度を高める「I形ジョイスト」を従来のツーバイフォー工法に組み合わせた技術です。長寿命を重視し世代を超えて住み継がれる住まいを実現できます。
三菱地所ホームで家を建てた人の評判・口コミ
三菱地所ホームさんでは当時、飲食店舗と老人が住むバリアフリーの住居とを両立させた事例がなかっただけに熱心に取り組んでいただきました。そして今でも気にかけて立ち寄ってくださり、相談相手にもなっていただいていることを大変心強く感じております。
引用:三菱地所ホームオーナー様の声「熱心な取り組みと、その後のうれしいお付き合い」
会社情報
| 会社名 | 三菱地所ホーム株式会社 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア7階 |
| 設立年 | 1984年7月2日 |
| 資本金 | 4億5000万円(三菱地所株式会社出資) |
| 年商 | 282億円(2021年3月末実績) |
| 従業員数 | 491名 |
| 公式サイト | https://www.mitsubishi-home.com/ |
おすすめのハウスメーカーについては下記の記事で詳しく解説をしています。
プロが選ぶハウスメーカーランキング-1万人以上に聞いたおすすめ住宅メーカー
ツーバイシックス(2×6)はどう?

ツーバイフォーと似た工法にツーバイシックス(2×6)工法があります。
この2つの違いは、用いられる角材の大きさの違いです。
- 2×4工法:38mm×89mm
- 2×6工法:38mm×140mm
ツーバイシックス工法で用いられる角材の方が幅が広いので、建物の強度が高まります。
また壁に約1.5倍の厚みが出るので、その分断熱材の厚みも増えて断熱性能が高くなるという特徴があります。
その他の特徴は、ツーバイフォー工法とほぼ同じと考えて良いでしょう。
まとめ
ツーバイフォー工法の住宅は、耐震性や耐火性の高さを持ちながら、低コストで建てられるのが魅力です。
しかし、間取りの制限などがあるので、自分の理想とする家の条件や、今後のリフォームについても考慮しながら決めていく必要があります。
ツーバイフォーの実績と技術が確かなハウスメーカーで安心できる家づくりをしましょう。
しかし多くのハウスメーカーがツーバイフォー工法に対応しているため、依頼先をどうやって決めればいいかわからずにいる方も多いかもしれません。
ハウスメーカー選びに不安があったら、まずは資料の一括請求にチャレンジしてみることがおすすめ。資料請求のために色々な会社へ自分で問い合わせする手間が省け、届いたパンフレットで一度に比較できます。
マイホームづくりは、人生の中でそう何度も経験することがない大きな決断です。後悔することがないよう、じっくり情報収集してくださいね。
【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒
【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒
※令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成