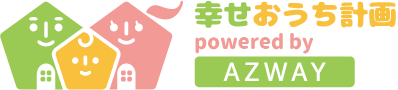promotion
「軽量鉄骨住宅を建てたいけれども、どのハウスメーカーを選べばいいんだろう?」
「軽量鉄骨住宅のハウスメーカーを比較するポイントを知りたい」
「家選びで失敗しないために意識することは?」
軽量鉄骨造で建てられた家は丈夫であり、戸建住宅でよく用いられています。多くのハウスメーカーが手掛けているからこそ、どこで購入するべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
ハウスメーカーによる違いは、デザインだけではありません。
それぞれ強みや、保証内容が異なっているため、しっかり比較することをおすすめします。
そこでこの記事では、以下の内容について解説します。
- 軽量鉄骨住宅を扱うハウスメーカー
- ハウスメーカー比較のポイント
- 軽量鉄骨住宅のメリット・デメリット
- 失敗しないための注意点
後悔のないマイホームを手に入れるために、ぜひ参考にしてください。
また、解説に入る前に家づくりを失敗させないために1番重要なことをお伝えします。
それは、1番最初にマイホーム建設予定に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。
これから30年、40年と生活をするマイホーム。絶対に失敗するわけにはいきません。
家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先に住宅展示場やイベントに足を運んでしまうこと。
「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでしまった)家を見つけ、営業マンの勢いに流され契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。
はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。
もっと安くてもっと条件良く高品質の住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、何百万円、場合によっては1,000万円以上の大きな損をしてしまうことになるのです。
マイホームは人生の中でもっとも高い買い物。 一生の付き合いになるわけですから、しっかりと情報収集せずに住宅メーカーを決めるのは絶対にやめて下さい。
「情報収集しすぎ」と家族や友人に言われるくらいで丁度良いのです。
とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いでしょう。
そんな背景もあり、昨今では、条件にあった住宅メーカーにまとめて資料請求を依頼できる「一括カタログサイト」が増えていますが、中でもおすすめなのが大手が運営する下記の3サイトです。
この3サイトはどれも、日本を代表する大手企業が運営しているため審査が非常に厳しく悪質な住宅メーカーに当たるリスクを避ける事ができます。
また、カタログを取り寄せたからといって無理な営業もなく気軽に利用でき非常にメリットが大きいサービスです。
3サイトの中でどれか1つ使うなら、
また、より慎重に絶対に失敗したくない方は絶対に工務店、絶対にハウスメーカーと決めつけずに1社でも多くの会社から資料を取り寄せてしまいうのがおすすめです。
「ハウスメーカーで考えていたけど、工務店の方が理想な家づくりが出来るし高品質だった」
「工務店で考えていたけど、意外と安く建てられる思いもよらないハウスメーカーと出会えた」
このような事は非常に多くあります。
また、なるべく多くの会社で資料を取り寄せることでメーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。
SUUMO・・・工務店のカタログ中心
家づくりのとびら・・・ハウスメーカーのカタログ中心

【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒

【工務店中心】SUUMOの無料カタログはこちら⇒ 
【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒
それでは解説をしていきます。
もくじ
鉄骨住宅とは?軽量鉄骨と重量鉄骨の違いも解説

戸建てには軽量鉄骨が一般的だと言う話を聞いてハウスメーカーを探し始めたものの、そもそもどのような家か理解していないという方もいるのではないでしょうか?
鉄骨住宅とは、柱や梁に鉄骨を用い、骨組みを作っている住宅です。構造の大部分が木材である木造に比べ頑丈であり、戸建て・マンション・ビルといった幅広い用途で使える点が注目を集めています。
鉄骨住宅は、鋼材の厚みによりさらに2つに別れます。
- 軽量鉄骨
- 重量鉄骨
それぞれ特徴を解説します。
軽量鉄骨の特徴
軽量鉄骨は、鋼材の厚みが6mm未満の鉄骨を使っています。鋼材が軽いため、建築費用がおさえられ、狭小地でも部材を運びやすいのがメリットです。
軽量鉄骨造ではプレハブ工法を用いることで、高品質・低コスト・短納期を実現できます。
プレハブ工法では、部材のほとんどを工場で加工し、最後の組み上げだけを現地で行います。これにより、職人の腕によってばらつきの出てしまう品質を安定させられるのです。さらに部材を大量生産できるため、コスト削減や納期の短縮といったメリットもあります。
部材が重い重量鉄骨造では、プレハブ工法を用いられません。2階以下で鉄骨造の戸建住宅の場合、多くのケースでプレハブ工法を用いた軽量鉄骨造を採用しています。
ただし、軽量鉄骨造の場合、鋼材が薄いぶん、重量鉄骨より強度が落ちます。これを補強するためにより多くの柱や梁を必要とするので、デザインの自由度では劣るのがデメリットです。
重量鉄骨の特徴
重量鉄骨は、一般に鋼材の厚みが6mm以上の鉄骨を使っています。鋼材が厚い分強度が出しやすく、3階以上の住宅でよく用いられています。
また、鋼材が厚い分、柱が太く頑丈になるため、より少ない本数で家の骨組みを作れるのがメリット。柱の数が減らせる分、広い空間を確保するのに向いています。建築の自由度が高く、希望を叶える住宅が実現しやすいでしょう。
鋼材に合わせて壁も厚くなる傾向があるため、軽量鉄骨より遮音性が高いのも魅力です。
一方で鋼材が厚い分、建築費用が高くなりやすいのがデメリット。さらに、骨組みの重量が重くなるため、地盤の補強工事が追加でかかる点も要注意です。
軽量鉄骨住宅ハウスメーカーランキング5選を特徴や坪単価まで紹介!

それでは軽量鉄骨住宅を扱っているハウスメーカーにはどんな会社があるのでしょうか?
軽量鉄骨住宅を扱うハウスメーカーをまずは5つ紹介します。
- ダイワハウス
- 積水ハウス
- ヘーベルハウス
- セキスイハイム
- パナソニックホームズ
それぞれ強みを紹介するので、気になるところを探してみてください。詳細が知りたいなと思った会社は、ホームページを確認したり資料請求したりすると良いでしょう。
1.ダイワハウス
- 坪単価:80万円~150万円程度
ダイワハウスの軽量鉄骨住宅は、耐震性能が強みです。一階部分には重量鉄骨も用いて軽量鉄骨と使い分けることにより、強度と経済性を両立しています。
たとえば、提案しているモデルの一つxevoΣでは、震度7の地震を4回繰り返しても耐震性能を維持できるという結果が実証されました。
さらに、ダイワハウスで用いられる鉄骨は自動車のボディーにも用いられている防錆処理を採用しています。鉄の強度を下げる錆への対策をしっかりと行うことで、耐久性をより高めているのも特徴です。
200のプランに、5つの外観と8つのインテリアスタイルを組み合わせて好みの住宅をセミオーダーできたり、木造とRCづくりを組み合わせたりできる提案の幅の広さも魅力でしょう。
2.積水ハウス
- 坪単価:60万円~120万円程度
積水ハウスは、環境と共生する住まいづくりをしています。
熱が逃げやすい窓にはオリジナルのSAJサッシを採用し、高断熱の住居を実現。夏は涼しく冬は温かい部屋作りをして、省エネに貢献しています。
さらに、太陽光発電や燃料電池を取り入れ、自家発電することで、エネルギーを生み出せる「創エネ」にも積極的です。
地震対策には10年以上の研究により生み出された「シーカス」というシステムを採用。新幹線にも用いられている高減衰ゴムをダンパーに採用し、地震を熱エネルギーに変換することで吸収します。
構造に自信があるからこそ、初期30年は無料点検を実施し、保証をつけています。その後も必要な点検や工事を提供して、建物がある限り保証が延長できるのも魅力です。
3.ヘーベルハウス
- 坪単価:80万円~130万円程度
ヘーベルハウスの住宅は、外壁に採用している独自の構造体「ヘーベル」や、断熱材で鉄骨を覆い、露出させないことでサビを避け、高い耐久性能を実現しています。鉄骨部材の耐用年数は60年以上と、かなり長めです。
地震以外の災害への強さも売りにしており、火災や風水害による被害も小さくなるよう、部材、構造にこだわりを持っているところも魅力です。万が一のときに、生活を復旧するところまで考えた取り組みが評価され、ジャパンレジリエンスアワードを4年連続受賞しました。
また、長く済み続けたいという要望に答え、60年間の無料点検のほか、初期保証は30年。その後も60年間の保証が続きます。相談窓口は24時間365日受け付けているため、いざというときのアフターフォローも手厚く、心強いでしょう。
4.セキスイハイム
- 坪単価:60万円~150万円程度
セキスイハイムは、工場と連携して実現した「ユニット工法」が強みです。
屋根のある工場内で部材を組み立て、現場作業を最低限にすることで、組立時の雨による部材の劣化や歪みを回避しています。基礎工事を終えたあと、現場での作業はわずか1日で、屋根・窓・ドアを取り付けた状態まで組み上げまで完了するとのことです。
工場では、コンピュータにより25,000点の部材をリアルタイムで管理し、高品質の安全な家造りを実現しています。すべてのデータは引き渡し後も残るため、不具合が起きたときの対応も迅速です。
そのほか、外壁には磁器を採用を採用しているのもメリット。紫外線や酸性雨にも強く、雨が降るたびに表面の汚れが落ちるため、メンテナンスの手間がかかりません。実際に築26年経っても美しい外観を保っている実績があります。
5.パナソニックホームズ
- 坪単価:80万円~130万円程度
パナソニックホームズも耐震性能に自信を持っており、独自の保証をつけています。
直近の阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震では、倒壊した建物はありません。万が一立替や補修が必要になった場合には「地震あんしん保証」により、原状復帰を約束しています。そのほか、地震保険もつけられるので、建物以外の補修に保険金を使うことも可能です。
外壁には「キラテックタイル」という独自加工したタイルを採用。埃や塵の吸着を抑えるほか、排気ガスの汚れがつきにくく雨水で流れやすいため、60年メンテナンスフリーで住み続けられます。
間取りは15cm単位で調整可能であり、敷地を無駄なく使えるのもメリットです。さらに、基礎の内部まで断熱処理を施すことで断熱性を高めており、電気代を26%削減できる省エネ性の高さも見逃せません。
プロが選ぶハウスメーカーランキング-1万人以上に聞いたおすすめ住宅メーカー
ローコストで建てられる?安い軽量鉄骨ハウスメーカー2選

軽量鉄骨は木造と比較するとどうしてもコストが高くなりますが、その中でも比較的安く建てられるハウスメーカーを2社ご紹介しましょう。
- トヨタホーム
- サンヨーホーム
それぞれの特徴を解説します。
1.トヨタホーム
- 坪単価:55万円~120万円程度
トヨタホームは、トヨタグループが持つ鉄の知識を集結した家造りが特徴です。柱と梁にボルトを使わず、溶接することで高い耐震性を実現しています。
車作りの技術を活かした鉄骨の防サビ加工の品質に自信を持ち、床下のサビは20年以上発生しなかったという実績もあります。
さらに、内装の腐食やカビなどの原因となる湿気対策も万全です。壁と床下、屋根への通気性を高め、長く住みやすい住まいを提供しています。
家造りの8割以上の工程を工場で進めることで、天候や施工場所によるばらつきを抑え、安定した品質の家屋を作っている点も特徴です。
トヨタホームは車のトップメーカーであるトヨタグループらしい特徴もあります。太陽光発電で作った電力を車に蓄え、停電時に車から給電できる設備を提供しているのがユニークなところです。
非常時には車の電気で家中の電力をまるごと復活できます。
2.サンヨーホームズ
- 坪単価:70万円~100万円程度
サンヨーホームズは、軽量鉄骨づくりと鉄筋コンクリート造のよい点を組み合わせたハイブリット構法を強みとして、特許も出願しています。
これにより、軽量鉄骨の強みである低コスト・短納期と、RCづくりならではの丈夫さを両立しました。軽量鉄骨造単体で住宅を建てるのに比べ、開放感のある大きな空間づくりを可能にしています。
さらに、サンヨーホームズは「年単価」の安い住居をコンセプトにしている点もメリットです。初期費用だけでなく、光熱費やメンテナンス費などの維持費も考慮にいれ、トータル費用で見たときのコストパフォーマンスが高くなるようにこだわりを持っています。
また、外壁材やドアの形などの選択肢が多く、デザインの組み合わせは10,000とおり以上にのぼります。こだわりのマイホームを作りたい方にはサンヨーホームズがぴったりです。
軽量鉄骨住宅のハウスメーカーを比較するポイント6つ

ここまで紹介したとおり、軽量鉄骨造を取り扱うハウスメーカーは数多くあります。そのため、どこに依頼するべきか悩んでしまうのではないでしょうか?
ハウスメーカーを比較するときには、以下のポイントを確認しましょう。
- 価格
- 構造
- デザイン
- 耐震性能
- 保証期間
- アフターサービス
順番に解説します。
1. 価格
家は生涯のなかでも最も高額な買い物の一つであるため、価格は重要な要素です。必ず複数のハウスメーカーから見積もりをもらい、内容を比較するようにしましょう。
複数の見積もりを見比べれば、料金だけでなく、その価格が妥当であるかも判断しやすくなります。安い代わりに間取りやデザインに制限があったり、キッチン・トイレなどのグレードが低く設定されていたりするかもしれません。
一見安そうに見えても、基本費用を抑えているだけでオプションを加えたら他社より高くなってしまったというのはよくある失敗です。
最終的な額面だけでなく、提案内容も踏まえた上で価格を比較することをおすすめします。
2. 構造
検討している家の構造・工法も確認しておきましょう。
構造により、実現できる間取りや家そのものの性能は変わってきます。ハウスメーカーにより得意分野が異なるので、事前に把握して置くことが大切です。リフォームの幅も構造によってほぼ決まってしまうので、将来のライフスタイルも考えておくと後悔しません。
3. デザイン
せっかく自分の家を建てるなら、デザインも重要な要素です。
賃貸住宅とは異なり、あなた自身の好みに合わせた住宅を設計できるのが、マイホーム購入の大きなメリットの一つ。ホームページやパンフレットを見たり、住宅展示場に足を運んだりして、気に入ったスタイルを探しましょう。
壁紙や外壁だけでなく、光の取り入れ方や、目地の見せ方まで、各社こだわりを持っています。ぜひ隅々までデザインを比較してみてください。
4. 耐震性能
地震の多い日本だからこそ、耐震性能は確認しておきたいところです。
耐震性能は、「耐震等級」という指標で確認できます。3段階で評価され、数字が大きいほど揺れに強いことを表すものであり、それぞれ、以下の水準で規定されています。
| 耐震等級1 | 建築基準法の耐震性能を満たす |
| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられる |
購入するときの目安は、「長期優良住宅」認定の条件となる、耐震等級2以上です。
耐震等級3ならば、熊本地震で起きた2回の震度7の揺れにも耐えたという結果もあるため、お住まいの地域の地震リスクに合わせて選択しましょう。
5. 保証期間
ハウスメーカーはそれぞれ独自の保証をつけています。対象となる期間はメーカーにより異なるので、あらかじめ確認するのがおすすめです。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によれば、住宅の基礎と雨漏りに関して、最低10年間保証することが義務付けられています。しかし、さらに長く、幅広い範囲の保証をつけているハウスメーカーも多いです。
特に大手メーカーは30年保証をつけているところも多くあるため、ぜひ内容も含めて比較してみてください。
6.アフターサービス
ハウスメーカーは、独自のアフターサービスも用意しています。無料定期点検や24時間相談サポートなどを用意したり、メンテナンスも提供しているので、確認してみてください。
家は建てて終わりではありません。住み続けるために補修したり、異常がないか確認したりする必要があります。これら、住み始めてからかかる費用に影響するアフターサービスは、できるだけ手厚いものを選ぶのがおすすめです。
軽量鉄骨住宅のメリット6つ

ここでは、軽量鉄骨住宅を選ぶメリットを紹介します。主なメリットは以下の5つです。
- 建築コストがおさえられる
- 狭小地でも立てやすい
- 耐用年数が木造より長い
- 工期が比較的短い
- 品質が安定しやすい
- 虫が出にくい
それぞれ、具体的に解説します。
1. 建築コストが抑えられる
軽量鉄骨造の場合、重量鉄骨を用いるのに比べて基礎工事が簡易的なもので済むため、建築コストがさがります。さらに、軽量鉄骨造で多く採用されているプレハブ工法の場合、さらに費用を抑えることが可能です。
プレハブ工法とは、家の部材の一部をあらかじめ工場で制作し、組み立てのみを建築現場で行う工法のことです。規格化された材料を工場で作ることにより、大量生産ができ、部材のコストを下げられます。
さらに、組み立てにかかる人員を減らせることも、低コストに寄与しています。
2. 狭小地でも立てやすい
軽量鉄骨造の部材は比較的軽いため、人力でも搬入できます。このため、狭小地に住宅を建てやすい点もメリットです。
実際に10坪以下の狭小住宅でも、軽量鉄骨住宅を採用されているケースがあります。
3. 耐用年数が木造より長い
法律で定められている軽量鉄骨造の耐用年数は、部材の厚さが3〜4mmの場合でも27年。木造の22年に比べて、長めになっています。
柱に鉄が用いられているため、シロアリ被害のリスクも避けられ、より長い期間住み続けられるでしょう。
実際に軽量鉄骨造の住宅には30年保証をつけているメーカーも多く、耐久性が高い点はメリットです。
4. 工期が比較的短い
軽量鉄骨造なら、工期も比較的短くおさえられます。現場での材料加工を減らし、あらかじめ加工した部材を運び込むことができるからです。
間取りにもよりますが、鉄筋コンクリート造では約半年かかるところを、2〜3ヶ月で施工したケースもあります。
基礎工事を終えたあとの組み立ては1日で完了させるハウスメーカーもあり、早くマイホームが手に入るのは魅力的でしょう。
5. 品質が安定しやすい
イチから現場で部材を作り、組み立てる場合、職人の腕により品質が左右されます。一方で、軽量鉄骨造のプレハブ工法で、部材を工場で生産するならば、部材の品質は大きくばらつきません。
部材の品質管理も工場内で行っており、不具合が出るリスクを下げられます。職人による品質の差が出にくく、メーカーが謳っている品質の住宅を手に入れやすい点も、軽量鉄骨造のメリットです。
6.虫が出にくい
木造に比べると、軽量鉄骨造のほうが虫が出にくいと言われています。木造の家は部材に気が使われているので、虫が卵を産み付けやすくなるからです。
ただし、鉄骨を用いていても住環境や周辺の状況次第で虫が出てくることはあります。鉄骨ならまったく虫が出ないというわけではありませんが、増殖をおさえやすいという点はメリットといえます。
軽量鉄骨住宅のデメリット5つ

軽量鉄骨造の住宅には、知っておきたいデメリットもあります。代表的なものは以下の5つです。
- 断熱性が低い
- 防音性能は高くない
- 間取りが制限される
- 木造より費用は高い
- 場合により地盤の強化が必要になる
いざマイホームを建ててから、他の工法が良かったと後悔しないために、ぜひ理解しておきましょう。
1. 断熱性が低い
鉄骨造は、一般的に木造に比べて断熱性が低いと言われています。また、湿気を吸収してくれる木と異なる金属は通気性も低く、外気の影響を受けやすいのがデメリットです。
対策をしなければ、夏は熱く、冬は寒い住居になりがちです。軽量鉄骨で住居を建てるならば、断熱材を壁や床に入れたり、複層ガラスや樹脂フレームの窓を採用したりすると言った工夫が必要になります。
2. 防音性能は高くない
軽量鉄骨づくりの防音性能は木造とほぼ同等といわれており、そこまで高くありません。なぜなら、柱や梁以外の素材は基本的に木造建築と変わらないためです。
今まで鉄筋コンクリートの住居に住んでいた方であれば、音が響いて気になる方もいるでしょう。特に、交通量の多い道路沿いや、線路のそばなどに住む場合は、対策を考えるべきです。
防音効果の高い外壁や吸音材を採用した床を提案しているハウスメーカーもあるので、住環境によっては検討してみても良いでしょう。
3. 間取りが制限される
軽量鉄骨造の場合、重量鉄骨よりも強度が低いため、より多くの柱を建てなければいけません。これにより、空間を広く取りたい場合に、希望がかなわないことがあります。
3階以上の住居はそもそも施工ができず、重量鉄骨造が前提になることもあるでしょう。
また、軽量鉄骨造の壁は強度を高めるために、ブレースと呼ばれる補強部材が入っていることがあります。これは、柱に対して斜めに取り付けられるため、間取りが制限されるのがデメリットです。
リフォームをするときに壁を撤去できなかったり、そもそも柱が鉄のため全体の構造を大きく変えられなかったりすることは覚えておきましょう。
4. 木造より費用は高い
軽量鉄骨造は比較的費用がおさえられるとはいえ、木造に比べると高くなりやすい傾向があります。木に比べると加工が難しく、基礎や地盤の補強もより必要になるためです。
間取りや構造にもよりますが、木造に比べて坪単価5~10万円ほど高額になるでしょう。
5. 場合により地盤の強化が必要
建築予定の場所の地盤が弱い場合は、強度を上げるために改良工事が必要になることもあります。木造に比べると構造が重くなるため、工事が必要になる可能性はあがるでしょう。
地盤の改良工事を伴う場合、工法や坪数にもよりますが、30〜180万円ほど追加料金がかかります。これにより予算オーバーすることがないように、あらかじめ家を建てる土地を確認してもらうようにしましょう。
軽量鉄骨は工務店でも建てられる?

工務店で軽量鉄骨住宅を扱っていることは稀です。
軽量鉄骨では部材を工場生産し現場で組み立てる形をとっているため、ハウスメーカーのように大量生産が可能な体制でないと難しいという側面があるからです。
多くの工務店では一棟一棟自由設計でつくるオーダーメイド方式のため、木造が一番得意な工法となるのです。
また現場施工できる重量鉄骨や鉄筋コンクリート造なら扱っている工務店もそこそこあります。
軽量鉄骨住宅のハウスメーカー選びで失敗しないための注意点6つ

軽量鉄骨住宅のハウスメーカー選びで失敗しないための注意点を5つ紹介します。
- 展示場に行ってイメージを掴む
- オーナーの自宅見学をしたり体験談を聞いたりする
- 優先順位を決めておく
- 営業担当者との相性を確認する
- 複数のハウスメーカーを比較する
- 契約後の変更について確認する
大きな買い物になる住宅だからこそ、購入前の確認を怠らず、満足のいく拠点を作りたいものです。ここで紹介する点はすべて取り入れ、納得のいくマイホームを手に入れましょう。
1. 展示場に行ってイメージを掴む
まずは展示場に足を運び、イメージを掴みましょう。カタログだけでは壁の質感や床材の雰囲気はわかりません。目で見ることで、自分の好みに合うかどうかがわかってきます。
ただし、何も調べていない状態でいきなり住宅展示場に向かい、カタログを集めるのはおすすめしません。展示場に訪れると、担当者との打ち合わせを設けられたり、割引のオファーがあったりして時間を取られ、じっくり比較ができないからです。
カタログはハウスメーカーのホームページから請求できます。事前に自宅で内容を読み込んでから、イメージと実物があっているかを確認する目的で展示場にいくのがおすすめです。
2. オーナーの自宅見学をしたり体験談を聞いたりする
モデルルームを見て候補を絞ったあとは、そのメーカーの住宅を持っているオーナーの自宅見学をしたり、体験談を聞いたりするのをおすすめします。
実は、モデルハウスは大きめに設計されていることが多く、実際自分の土地に家を立ててみたら手狭だったというのはよくある失敗です。収納家具やインテリアが揃った状態の住居を見れば、より生活がイメージしやすくなるでしょう。
さらに、体験談まで聞けると、計画時には気づかない改善点を発見できるかもしれません。マイホームの先輩たちの知恵も取り入れることで、より満足度の高い住宅を建てられます。
3. 優先順位を決めておく
ハウスメーカーから話を聞くうちに、どの設備をつけようか悩んだり、予算が大幅にオーバーしてしまったりすることがあります。
提案が魅力的であるほど、すべて取り入れたくなってしまうかもしれません。家探しを始める前に、家族全員で優先順位をしっかり決めておくことをおすすめします。
- 家の広さ
- キッチンやお風呂のグレード
- 立地
- デザイン
- 太陽光発電や床暖房などの付加機能
など、譲れない項目をあげたうえで、予算オーバーしたときにどれを削るか話し合うことが大切です。
提案を聞いて優先順位を変更したくなった場合は、その都度家族で話し合いを設けましょう。
4. 営業担当者との相性を確認する
多くのハウスメーカーの場合、最初に接客してくれた営業担当者がそのまま担当になります。
営業マンとの相性が良ければ、意見を取り入れつつ住みやすい家を作りやすくなるでしょう。一方で、なかなか話の通じない担当では、ストレスが溜まるだけでなく、最終的な家の仕上がりにも満足できないかもしれません。
ハウスメーカーの営業は簡単に変更ができないので、信頼ができる人がいる会社を選ぶのもおすすめです。
担当者とは住居が完成したあとも関係が続きます。住宅の定期点検やリフォームを考えたときの窓口になるからです。
ずっと付き合う相手になるからこそ、営業担当についていきたいと思えるかをしっかり検討しましょう。
5. 複数のハウスメーカーを比較する
1社だけを決め打ちしてしまうと、値段が妥当か、保証は充実しているかなどを判断できません。メーカーにより強みも異なるので、しっかり比較する必要があります。
必ず複数を比較し、相見積もりを取るようにしましょう。最低でも3社は声をかけるのがおすすめです。
相見積もりのメリットは、コスパの良さを比較できるだけではありません。希望する条件を伝えて見積もりをとったときに、自分の想像を超えるプランを提案してもらえる可能性もあります。
提案の幅が広い戸建ての住宅を考えるならば、具体的なアイデアも含めて比較したほうが、満足のいくマイホームを手に入れやすいでしょう。
6. 契約後の変更について確認する
契約に入る前に、今後の変更が可能かどうかも確認しておきましょう。住居が現実的になってくるにつれて希望が変わるかもしれません。
契約後の変更に関しては、メーカーにより対応は異なります。
- 変更はまったくできない
- 追加費用で対応可能
- 変更箇所に制限あり
などの可能性があります。
万が一に備えて、変更幅、費用ともにすると安心です。
なお、着工後は部材を準備し始めているため、変更を受け付けてもらえないことも多いです。変更できたとしても、細かな部分にとどまります。
間取り、外壁の色など主要部分は確定してしまうと認識し、丁寧に図面を確認することを強くおすすめします。
まとめ
軽量鉄骨造を扱うハウスメーカーは多くありますが、それぞれ強みや提案しているスタイルには差があります。そのため、よく内容を比較して希望を叶えてくれる会社を探すようにしましょう。
特に軽量鉄骨造の場合、工夫をしなければ断熱性や遮音性が低くなる点に注意が必要です。品質が安定し、短納期・低コストになりやすいというメリットもあるため、弱点をカバーする提案をしてくれるハウスメーカーを探すと良いでしょう。
満足のいく選択をするためには、複数のハウスメーカーから資料を集めることが重要です。複数社の資料を提案を見比べるうちに、当初は想像していなかった希望が見えてくることもあります。ハウスメーカーによってデザインの特徴や得意な施工内容は変わるので、まずは資料の一括請求で情報を集めることから始めてみてくださいね。
【ローコスト住宅中心】LIFULL HOME’Sの無料カタログはこちら⇒
【ハウスメーカー中心】家づくりのとびらの無料カタログはこちら⇒
※令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成